ついに Spring Semester の成績が出そろった。
初めてだった前期は、てんやわんや取り組んだ結果ああなったが、後期はまあこんなもんだろう、という科目から、ちょっとショッキングなものまで幅ひろの結果となった。
とくに歴史でグレード2をくらったのにはこたえた。
ハンガリーでは5段階評価で、グレード1が落単となる。
以下、今期の戦績。(成績受け取り順)
5:Communication Workshop
5:Foundation of Psychology(心理学基礎)
Signed:Competency Test in a Foreign Language
4:Introduction to Economics(経済学概論)
5:Hungarian(ハンガリー語)
4:Statistics(統計学)
4:Introduction to Law(法学入門)
2:International Relations from 1815 to 1945(歴史)
3:Research Methodology II(研究方法論)
来期にむけて反省のため、おおまかに振り返る。
Communication Workshop
テストなし
この科目は、1週間の春休み前の週に設けられたインテンシブウィークに開催される1回こっきりの変則的なセミナーだ。
ディスカッションやスモールプレゼンを含んだ、朝8時~夕方5時までの長丁場の授業。
内容に関しては、詳しく以前書いたので割愛。
基本的には出席時間のみでグレードが決まるため、グレード5となった。
Foundation of Psychology:心理学基礎
テスト免除
成績を得るには2つの選択肢があり、毎回小テストを受けるか、テスト期間に最終試験を受けるかである。
小テストは11回あり、そのうち最低8回受けることが前提である。
私は10回受けたので、そのうち結果の良い8回分で成績が与えられた。
小テストは、講義資料をこのブログに散々まとめたので、毎回8~10割は取れたが、小テスト対応するだけなら、講義スライドを前日くらいから読んどくだけでもおそらく対応可。
講義内容としては前期に受けた哲学とも重なるところも多かった。
人生を営む上で知っておいた方が良い情報を学ぶという感じ。
授業初っ端の小テストを受けると生徒は皆出てってしまうので、出席者が少なすぎて寂しい限りの講義だった。
グレード5。
Competency Test in a Foreign Language
テスト免除
この科目は、例えば体育のように学部ごとに設けられたクライテリアで、0単位である。
英語・ハンガリー語を除く言語を「外国語」とし、そのひとつを卒業までに CEFR B2レベルの達成を課すものだ。
CEFR B2レベルを日本の英語教育で例えると、ざっくり高校卒業レベルである。
これ、ハンガリー人学生にとっては結構高いハードルであると思われる。
留学生は英語を母語としない限り、自分の母国語能力を証明すれば良いだけだが、私は最初その辺が良くわからず、前期にスペイン語を焦って履修した。
語学だけで、英語2回/週、ハンガリー語2回/週、スペイン語3回/週の講義数となってしまい、その上体育もあったので、予習復習が追い付かなくなり破綻した。
(スペイン語を諦めた)
言語能力の証明は、試験のある言語はそれを受ければ良いが、日本語能力試験はないため、私は日本の大学の卒業証明書と成績証明書をアップロードし申請を行った。
写真:完了したので Fulfilled になった。
ちなみに、卒業までに承認が必要な、こういった科目にあたるものが他にもあり、
体育、インターンシップ
が残っている。体育は2セメスター取る必要があり、私はもう1回履修する必要がある。
Introduction to Economics:経済学概論
テストあり
中間試験+期末試験+セミナーの合計で評価される。
テストに関しては以前書いた。
セミナーも試験前も準備がなかなか大変だったが、自分がいかに経済のことをわかっていなかったことを知る良い機会になった。
そもそも私の知識は、中学の社会 + TVニュースくらいだ。
政府が実施する金融政策や財政政策が、どうアウトプットに影響を与えるかが、数式を介して学ぶため、基本が良くわかった。
インフレが借金に有利など、ふわふわしていた知識も具体的な数値計算でクリアになった。
ただ、知っている経済用語を英語のそれと結びつける作業はやはり大変だった。
そもそも日本語でも知らない専門用語もいっぱいあり、日本語の説明を読んでも「?」ということが多々あった。
前期はお地蔵さまのように座っていたことを考えると、経済学のセミナーは積極的にしゃべったと方だと思うが、自分でも何言ってるかわからなくなることがあるので、スピーキングはまだまだである。
グレード4。
Hungarian:ハンガリー語
テストあり
評価は、ペーパーテスト50%、オーラルテスト25%、その他25%の合計100%である。
その他の評価項目は、4回のミニテスト、宿題提出状況、出席数などであるが、4回のミニテストをしっかりこなしていれば、まず及第点であると思われる。
私は欠席0、ミニテストは9割以上、宿題は全部提出していたので、「その他」は満点。
前期と比較すると、かなり文法が複雑になるのと、動詞が多様になるので、いかにその辺を頭に叩き込めるかが勝負となる。
ただ、日本人の多くは文法には強いだろうから、ペーパーテストはむしろ得点源になると思われる。
オーラルテストは、発声練習はもちろん大事だが、パートナー選びも結構重要である。
前期はやる気のないジョージア人がパートナーだったので、テスト30分前から練習するという行き当たりばったりな対応だった。
今回は日本人がパートナーだったので、毎日練習に付き合ってもらい、無難にこなすことができた。感謝感謝である。
次セメスターに、続きの講座があるそうだが、受けるか考え中。
(というか専門科目の日程次第)
グレード5。
Statistics:統計学
テストあり
この科目は復習が結構大変だった。
各セミナーのテーマに沿ったミニテストがオンラインプラットフォーム Moodleに設けられているため、授業終わりに毎回復習の意味で取り組んだが、とにかく時間がかかった。
写真:7回分ミニテストがあった
間違うと、なぜ間違っているか確認するのに時間がかかり、そもそも問題の英文が理解できなかったことも多々あったので、それも時間をかける要因となった。
写真:授業はエクセル作業が主
また、授業はほとんどエクセルシートのデータをいじくる作業が主だが、そこにも復習用に課題が付属しているため、それも毎週こなしたため、先のミニテストを合わせ、毎週かなり時間がかかった。
そしてテスト前になると、春休み前に学んだことなんてほとんど忘れてしまっていたので、これらの資料を復習することで、期末テスト対策とした。
正直、今学期一番グレード5を取れそうな科目だったが、準備にあと2日ほど足りなかった。日程計画が甘かった点といえる。
グレード4。
Introduction to Law:法学入門
テストあり
講義日程の変わりようについては以前ブツブツ書いたが、講義のおおまかな内容としては、
・法律と倫理間のジレンマの実例
・古代ローマ帝国の法律
・ルソー、ヒューム、ホッブスなどの思想
・EU の法律
・AI に関する法律
という感じだったかなと。
2年生で国際法の科目があるので、もう少しがんばりましょう。
グレード4。
International Relations from 1815 to 1945:歴史
テストあり
本日成績が出て、グレード2だった。
前期グレード5で終えられたせいで、落差にはちょっとショックだったが、自分なりに何がまずかったか以下の点を整理。
1.日程とエッセイの準備
1発勝負を意味する、第4スロットにテスト日程を登録したことで、こういった成績を受けても挽回の手段がないことが挙げられるかもしれないが、冷静に振り返っても、経済学と統計学がそれなりにウェイトを占めていたため、テスト期間中だけで対応するならば、この日程しか選択できなかったといえる。
学期中、普段からコツコツ準備する必要があるということだ。
2.テスト配点の変更
ロングエッセイ・ショートエッセイの得点比が、
前期 = 3:2
後期 = 3:1
となったことで、ロングエッセイにミスは許されない状況となった。
3.ロングエッセイのテーマ
与えられた「第1次大戦」のテーマは一番想定していなかった。(なので準備が甘い)
そもそも広いテーマなのに、取っ散らかった内容を書いてしまったこと。何なら次の時代のテーマのことまで書いてしまい、それが内容の 1/3 を占めたこと。
ガリポリの戦いや東部戦線、バルカンの戦闘と参加国、中東の状況など書くことはたくさんあるのに、それらを書かず、戦前のこと、戦後のことをだらだらと書いてしまった。
構成を考える段階で少し冷静さを欠いていたかもしれない。
結局、内容がフォーカスされてないことが今回の一番の問題だろう。
また、エッセイの準備すればするほど、初期に準備したものから記憶が薄れていく。
または、興味のないテーマから記憶が薄れていくので、これらの対策も必要である。
前期のロングエッセイは、たまたま準備したばかりのテーマが試験当日の課題となったため、うまく書けたにすぎない。
次回は自分の好きなテーマ以外であろうと、深く頭に叩き込んで、書き上げられる状態をいかに作り上げるかを普段から取り組むことが目標か。
以上!
グレード2。
Research Methodology II:研究方法論 II
テストなし
この科目は以前少しだけ思いを書いたが、ずっと成績が出ず、やっと本日アップされた。
グレード3の結果をもらって「ふーん」という感じだ。
本セミナーは、この先、論文を書くのに必要な知識を定着させることが目的である。
写真:未だにHomework III の成績は出ていない
課題の評価ウェイトが大きい科目だが、課題1、2でもう 7/10 点の評価をくらっていたので、成績には期待していなかった科目である。
しかし、私としては、Individual Home Assignment というメインの最終課題がしっかりできていれば、この科目での目的は達する。
で、評価は 38/50 点。
また7割かよ!と思い、フィードバックを見たが、26か所の指摘があり、そのうち
・8か所は英語に関して
・5か所は reference に関して
残りの13か所はいろいろだが、
いや、「?」とフィードバックされても、こちらも「?」なんですけど。
毎回、フィードバックには、評価者が何がわからないのか、こちらもわからない、というものが結構あった。
まあそういうのは置いといたとしても、今回受け入れられないフィードバックがあった。
前期に引き続き、北朝鮮の核開発について書いたのだが、
北朝鮮政府の核開発に関する政策姿勢が、
・列強の影響(主に米国・ソ連)
・歴史的イベント(米国のイラク侵攻や 9.11)
・関連技術習得(主にCNCマシンの技術習得)
の3本立てのファクターが政策決定にどう影響、または後押ししたか、
という内容で構成したのだが、CNCマシンに関するチャプターを全否定されたことだ。
これだから文系は~とか死語も言いたくなるが、普通の人はCNCマシンが何か知らないだろうし、それをあの経済状況の国が習得することの驚きも伝わらないのかもしれない。
しかしその重要性は伝わるように、いかに北朝鮮が国を挙げてまでCNCを祭ったプロパガンダを盛んに行ったことも、ミサイル制作に欠かせない技術だということも書いたんだが。
技術的裏付けがあったから、国内・国際舞台での強気の態度が取れるというものだ。
講師にそれが伝わらなかったなら、まあしょうがない。私の英語力か問題は。
あと、出欠も評価対象なので状況をチェックできるのだが、1日欠席、1日「?」となっている。1回欠席したのでもちろん「欠席1日」は良いが、「?」ってなに?
写真:出欠状況に「?」がある
このセミナーの一番良くない点は、せっかくフィードバックを受け取りながら授業に参加して、それらを吟味しても、論文の書き方として、正しい方向が見えない、また完成形も見えないまま、という点に集約される。
結果、マスターの友人に聞いたり、AIに聞いたり、自分で調べて作成するが、評価者のお眼鏡にかなうものではない、を繰り返した。
ただ、Mandatory reading は、とても興味深い本ばかりだった点は良かった。


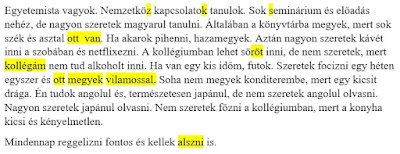












0 件のコメント:
コメントを投稿